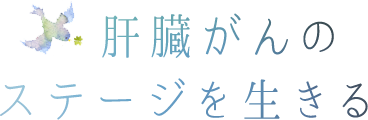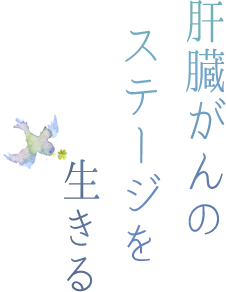肝臓がんの進行リスクがある肝硬変になる原因とは
このページでは、肝臓がんへの進行の可能性がある、肝硬変の原因や症状についてまとめています。
肝臓がんの前段階とされる病気が、肝硬変です。肝硬変を放置することは、そのまま肝臓がんを引き起こす原因となります。
【肝硬変とは】
肝炎などが原因で肝細胞が破壊と再生を長期間に渡って繰り返すことで、肝細胞が線維化し、肝臓が小さく硬くなる疾患。
C型慢性肝炎が発症した場合、その7割に病状の進行が伴う。さらにその3~4割は10~30年の間に肝硬変へと進行する。
 肝硬変は、肝臓がんへと移行しやすいという重大なリスクがあります。
肝硬変は、肝臓がんへと移行しやすいという重大なリスクがあります。
それだけでなく、合併症リスクもあります。
肝硬変になると、肝臓へ血液を運ぶ門脈の流れが悪くなります。
うまく通ることができない血液は食道の静脈へと迂回するのですが、この症状が進むと食道静脈瘤を引き起こし、下血や吐血を起こします。
また、肝臓の機能が低下すると、処理しきれなかったアンモニアが脳に溜まり、
異常な行動や昏睡などの症状を呈す「肝性脳症」を引き起こすこともあります。
その原因
ほどんどの場合は肝炎ウイルスによる、慢性肝炎が原因となっています。
肝硬変の症例中、60.6%がC型肝炎、9.5%がB型肝炎を原因としています(1994年日本大学調べ)。
なおアルコール性の肝硬変は、全体の16.7%。アルコール性の肝硬変は肝臓がんへの進行リスクはそれほど大きくないのですが、日常的に飲酒量の多い人がウイルス性肝炎にかかった場合は、肝臓がんへ移行する可能性が大きくなるようです。
その症状
初期段階では肝機能が保たれているため、自覚症状がありません。
「非代償性肝硬変」へと移行すると、倦怠感、脱力感、疲労感、腹部膨満感、吐き気、尿の色が濃くなるといった症状が現れます。
肝機能に余裕がなくなっている証拠です。
さらに進行すると、黄疸や腹水、吐血、肝性昏睡など、合併症からの症状も現れるようになります。
肝炎、肝硬変の初期段階で、進行を少しでも食い止めるよう努力することが必要です。
慢性炎症の抑制によるがん予防の可能性
がんと慢性炎症との間には、疫学的な関連性が知られてきました。肝臓がんの場合、C型肝炎ウイルス感染による慢性炎症の関与が知られます。そこで注目されているのが、免疫調整機能を持つ日本発の特許成分「米ぬか多糖体」の抗炎症作用です。
このサイトでは、がんに対する免疫向上・調整機能などが、さまざまな試験や報告で裏付けされている日本発の特許成分「米ぬか多糖体」を、注目成分として特集しています。