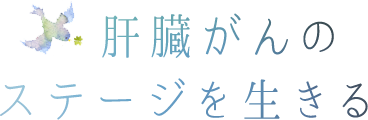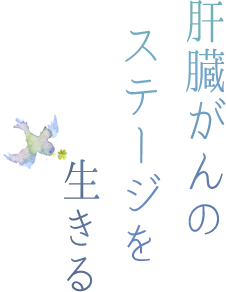がん治療の基礎知識(高山忠利先生)
がんの進行度合いによって適切な治療方法が異なる肝臓がん治療。肝臓がん治療について詳しく紹介している記事についてまとめました。
(解説:高山忠利先生/出典:がんの先進医療:http://gan-senshiniryo.jp/standard/post_1349)
記事の要約
- 医学の進歩により、肝臓がんの治療方法は確立されつつある
- 肝臓がんと闘ためには、その治療方法についての正しい理解が不可欠
- がんの除去後も、再発を防ぐために定期的な検査を受けることが重要
記事のポイント
「がん治療の基礎知識」記事について、ポイントとなる部分を抜粋して紹介します。
肝臓がんの徐々に死亡率が低下
肝臓の細胞以外の胆管からも発症する肝臓がん。数年前までは発生数が増加していましたが、徐々に減少し始め、死亡率も低下しています。現在は超音波検査でがんをチェック。その後がんが見つかった場合に、CT検査あるいはMRI検査で詳しく調べるそうです。
肝臓がんのステージに合わせて治療方針を決定
腫瘍の個数や大きさ、脈管侵襲の有無、リンパ節転移の有無などを基準にして、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ A期・Ⅳ B期に分類されている肝臓がん。肝臓機能がどれほど損傷しているのかをA・B・Cの3段階で示す「肝障害度」も一緒に考慮して治療方針が決定されています。治療方針は手術・ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法・肝動脈化学塞栓(そくせん)療法・化学療法などがあります。
肝機能が正常でがんが3個までの場合は「手術」
肝障害度A・Bで、大きさを問わずがんが3個までの方の場合、肝臓の切除手術を行なうケースが少なくありません。施術手術の場合、ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法や、肝動脈化学塞栓(そくせん)療法と比べて、再発率が低いことが分かっています。ただし、がんが4個以上あった場合、施術手術を受けても再発するおそれが高いそうです。
がんが3cm以下で3個以内の場合は「焼灼療法」が選択可能
ラジオ派の発信による高熱でがんを死滅させるラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法。超音波画像で肝臓がんの位置を確認しながら、電極針を患部に刺して高周波の一種であるラジオ波を発信します。皮膚を切開する必要がないので、治療によるダメージが少ないのが特徴的。ただし、この治療法が適しているのは、がんの大きさが3cm以内で、3個以内の方です。
がんが3cm以上や4個以上の場合は「肝動脈化学塞栓療法」
がんが4個以上あると手術やラジオ波焼灼療法では治療できません。肝動脈を塞いでがんを死滅させる肝動脈化学塞栓療法が用いられます。肝動脈化学塞栓療法は脚の付け根にある血管からカテーテルを入れて、がん近くで抗がん剤を注入した塞栓物質で血管を塞ぐ手術です。手術やラジオ波焼灼療法を受けた後に再発して、がんが増加してしまった場合に用いられています。
肝動注と分子標的薬治療がある「化学療法」
肝臓脈化学塞栓療法が行なえないほど肝機能が低下している場合、肝動脈に入れたカテーテルから抗がん剤を注入する肝動注化学療法が用いられます。肝動脈化学塞栓療法と違って、塞栓物質で血管を防ぎません。また、転移により手術や局所療法の対象外となった肝臓がんの場合、薬でがん細胞の増殖を抑える分子標的薬で治療を行ないます。分子標的薬であるソラフェニブの治療が、がん細胞増殖の抑制に効果が期待できるそうです。
再発を防ぐためには治療後の定期検診が大切
術後に再発した場合は、全身疾患と考えて抗がん剤を投与する治療が行なわれます。ゲムシタビンとシスプラチンと呼ばれる抗がん剤を併用するGC療法を実施。強い副作用はありませんが、吐き気やけん怠感・骨髄抑制などの症状がでることがあります。再発を防ぐためにも定期的に病院で肝臓の検査を受けましょう。2~3ヶ月1回の頻度で超音波検査を受け、1年に2回CT検査を受けることをおすすめします。
再発した場合に行われる「放射線療法」
肝臓がんは再発しやすいがんのため、手術やラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法などで一度除去しても、再度肝臓がんを発症するケースがあります。その場合、放射線量で治療を行なうそうです。
記事の総評
肝臓がんは再発しやすいがんです。一度手術やラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法などを受けて、除去してもがんによる脅威が完全に去ったとは言えません。残っている肝臓にがんが発生するおそれがあるので、治療後は定期的に肝臓の検査を受けましょう。万が一がんが見つかった場合でも、早い段階で発見できるため、初期段階で対処することが可能です。
記事を執筆・解説した先生
高山忠利先生(日本大学医学部長・大学院医学研究科長・消化器外科教授)。世界初の肝尾状葉単独切除に成功し、「高山術式」を確立。手術実績は、肝臓がんを筆頭に、胆道、膵臓など年間300例に及ぶ。