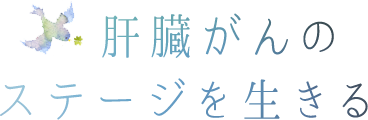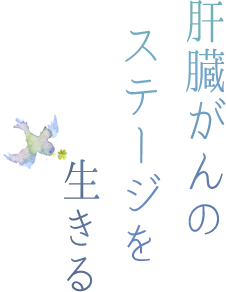肝臓がんの手術を受けた後の食事方法
肝臓がんの手術を受けた後の食事について
このページでは、肝臓がんの手術を受けた人の食事について紹介しています。
肝臓がんの手術を行った後に、気を付けなければならないことの1つに挙げられるのが、合併症の発症。その予防策として、術後に出来るだけ早く運動を始めて、腸などの動きを回復させることが重要となります。そのためにも食事となり、どのようなものを食べると良いのか、逆に食べてはいけないものなどを分かりやすく解説していくので、参考にしてみて下さい。
肝臓がん術後の食事で意識したい基本
食事はいつから食べてもいいの?
肝臓がんの手術は、がん病巣がある肝臓の一部を摘出する方法が一般的。切り取った肝臓の割合がそれほど大きくなければ、手術から2、3日で食事をすることが可能です。範囲が大きい場合は、もう少し時間がかかり、1週間程度かかる場合があるので注意しましょう。
固形物と点滴はどちらがおすすめ?
栄養を摂取する方法は、食事だけでなく点滴による方法も考えられますが、できれば食事をする方がおすすめ。その理由は、高血糖になってしまうからです。点滴で栄養を補給すると、体内の水分量が多くなってしまいます。肝硬変を合併していると、代謝の機能が低下していることが考えられ、その結果、高血糖になってしまうのです。
また、高血糖だけでなく、食事を取ることにより、消化器官の動きを正常に戻すことができるため、なるべく早く食事をする方が良いでしょう。
肝臓がん術後に食べてもOKな食品
肝臓がんの手術を受けた後の食事で何を食べればよいのかというと、簡単に言ってしまえば、基本的には好きなものを食べて構いません。もちろん、栄養バランスが良いということは大前提ですが、食べたいものを食べましょう。肝臓を再生するためには、良質なたんぱく質を摂取することが良いため、たんぱく質を取ることが重要。中でも植物性のたんぱく質が豊富な大豆がおすすめです。
その他では、ミネラルがたくさん含まれているわかめや昆布などの海藻、ビタミンが豊富な緑黄色野菜を食べるようにしましょう。
肝臓がん術後に食べてもNGな食品
先ほど紹介したように、肝臓がんの手術を受けた後に食べてはいけないものは基本的にはありませんが、肝硬変を併発している人は注意が必要です。
合併症別に合わせた食事の仕方
肝硬変の人は、アンモニアを代謝する機能が低下しており、血液の中にあるアンモニアの濃度が上がってしまう危険性があります。アンモニア濃度が上がってしまうと、最悪の場合、意識障害が発生してしまうことも。
では、血液中のアンモニア濃度を上げないためには、どのような食事をすればよいのでしょうか。まず1つ目は、たんぱく質を摂取しすぎないことです。ただし、あまりに制限しすぎるのもよくありません。服用している薬などを元に、医師に確認するようにしましょう。2つ目は、便秘をしないこと。便秘になると、アンモニアがたまる原因となります。フルーツや果物といった水に溶けやすい食物繊維を含んだ食材を多く食べるように心がけましょう。