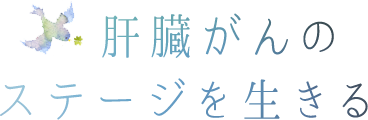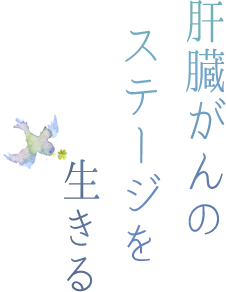良性と悪性の違いは?
肝臓にできる腫瘍について、良性のものと悪性のものの違いを解説しています。
「肝臓に腫瘍が見つかった」というと、すぐに肝臓がんを想像される方が多いと思いますが、「腫瘍」という意味は「できもの」に近く、変異のことを指します。
そもそも良性と悪性とは?
腫瘍は、良性のものと悪性のものに分けられます。このうち、悪性腫瘍と呼ばれるのが「がん」です。良性腫瘍はがんではないことをまず理解しておきましょう。
皮膚に突然ホクロができることがありますが、新しくできたホクロが必ずしも、がんとは限らないのと同じです。
しかし、「良性」という言葉が付いていますが、良性腫瘍も体の変異ですので、無視することはできません。
良性腫瘍とは
では、良性腫瘍ががんではない腫瘍とすれば、どんなものなのでしょうか?良性腫瘍には以下のようなものがあります。
- 肝嚢胞
- 肝血管腫
- 肝細胞腺腫
- 限局性結節性過形成
- 炎症性偽膿瘍
- 血管筋脂肪腫
これらは、基本的には正常な細胞が集まってできた腫瘍です。肝臓に水が溜まっているもの、膿がたまっているものなどがあります。
非常に大きい場合は破裂などのリスクがありますが、日常生活にはほとんど影響はありません。
悪性腫瘍の可能性は?
ただし、良性であっても実は悪性腫瘍であったケースや、後に悪性化してがんになるリスクも否定はできません。
たとえば、肝細胞腺腫は悪性化する可能性があります。特に、経口避妊薬を使っていた人に悪性化のリスクが大きいと言われています。
また、限局性脂肪化と初期の肝臓がんなど、見分けるのが難しいものがあります。良性腫瘍だったとしても、ある程度の経過観察が必要なのは言うまでもありません。
気になる症状があれば、腫瘍マーカーやウイルスマーカーなどで肝機能の状態を調べ、ウイルスの特定などをしたり、超音波検査、CT、MRI検査での画像診断を行います。最終的には、肝臓に針を刺して腫瘍の一部を採取する、肝生検で診断を確定することができます。