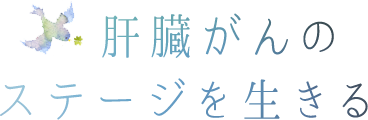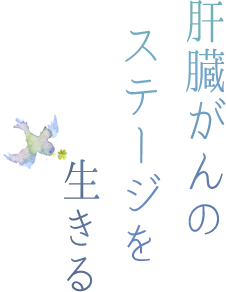ステージ3の肝臓がん
肝臓がんの後期にあたる、ステージ3の定義や治療法、余命や生存率についてデータを集めてみました。
【肝臓がん】ステージ3の症状と治療法
肝臓がんのステージの後期にあたる、ステージ3。この段階までくると、肝臓がんがかなり進行してしまっています。
肝臓がんはT因子、N因子、M因子と呼ばれる3つの因子の状態で定義されます。
ステージ3の定義は以下のようになっています。
- T因子のうち、いずれか1つがあてはまる(腫瘍個数が1つ、腫瘍径が2cm以下、脈管侵襲がない)。
- N因子は、あてはまらない(リンパ節への転移がある)。
- M因子は、あてはまらない(遠隔転移がある)。
T因子が複数あてはまったとしても(腫瘍自体の進行が軽度でも)、N因子があてはまるとステージ3になります。
つまり、腫瘍の大きさに関わらず、リンパ節へ転移するとステージ3になります。
ステージ3の生存率
がんについては、ステージごとに余命の目安があるわけではありません。その代わりに、5年生存率というものが使われます。
肝臓がんステージ3の5年生存率について、1997~2000年に初回入院した方の症例から計算すると、24.8%となっています。
ステージ3まで進行してしまうと、5年間生存できる確率が4分の1ということになります。
肝臓がんは再発率が高く、生存も非常に難しいのです。
また、ステージ3まで進行すると、腹水や黄疸などの症状が現れることもあります。
ステージ3の治療法
まず可能な限り行われるのが切除手術です。
とは言えステージ3の肝臓がんは病巣の拡大が見られることが多く、医師から「手術は難しい」と宣告されることがあります。
手術が難しい場合、肝臓の動脈にゼラチンスポンジを詰めて、がん細胞への栄養を遮断する、
肝動脈塞栓術という方法が使われます。
肝臓がんは再発率が高く、また再発を繰り返すうちに肝動脈以外から栄養を摂るようになり、
治療効果が弱まってしまうこともあります。
そのため、切除後はいかに再発を防ぐが問題となります。
【肝臓がん】ステージ3に関する注目記事をピックアップ
肝臓がんは、ほかのがんが転移して見つかることが多いのが特徴で、発見されたときには、すでにステージ3まで進行してしまっているケースもあります。ここでは、ステージが進んだ肝臓がんに対して有効的な治療法や、肝臓がんの治療を専門に行う名医のインタビューなどを掲載しています。ぜひ参考にしてください。
肝臓がんが進行したら?肝臓がんのダウンステージング
肝臓がんが発見されたときには、すでにステージ3の状態ということは少なくありません。ステージ3はがん細胞が大きくなり切除が難しい状態ですが、切除を行なう方法があります。それは「ダウンステージング」という方法です。今回は肝臓がんのステージレベルを下げる、「ダウンステージング」の方法についてインタビューした記事をまとめました。
(出典元:Medical Note/https://medicalnote.jp/contents/170118-001-ZI)
記事の要約
- 肝臓がんのダウンステージングで根治できる可能性も
- 化学療法などを使ったダウンステージングの方法
- ダウンステージングにより5年後生存率が改善
記事のポイント
肝臓がんのダウンステージングで根治できる可能性も
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれており、肝臓がんの自覚症状が出たときにはすでに進行していることが多いです。肝臓がんの根治は、肝臓を切除するのが最善と言われています。しかし、がん細胞が大きすぎて切除ができないこともあるのです。
そこで、肝臓がんを化学療法などで小さくして切除ができる状態にする「ダウンステージング」が行なわれます。進行した肝臓がんに対して、ダウンステージングはその有効性にもかかわらず、まだ普及していません。医師がダウンステージングを知っていれば、生存期間を大きく延ばしたり、根治できる可能性を上げたりできるのです。
化学療法などを使ったダウンステージングの方法
肝臓がんのダウンステージングの方法は、肝動脈塞栓術や肝動注化学療法、分子標的薬を使った方法があります。 肝動脈塞栓術はがんの近くまでカテーテルを通して、大量の抗がん剤と血管を塞ぐ作用のある薬を注入する方法です。血管を塞ぐことでがん細胞のみを死滅させることができ、さらに抗がん剤を投与することで死滅効果を高められます。
肝動注化学療法は、抗がん剤を肝動脈から直接肝臓に注入する方法です。肝臓に直接薬を入れるので、抗がん剤の量が少なくて済み、副作用も軽くなります。 最後に分子標的薬は、がん細胞を増殖させたり転移させたりする物質のみに効果のある薬です。抗がん剤と異なり、重い副作用が出るリスクを下げることができます。
ダウンステージングにより5年後生存率が改善
肝臓がんにダウンステージングを行ってから切除した例と、行わずに切除した例で5年生存率を比較した結果、生存率に大きな差が出ました。ダウンステージングを行った例では、5年生存率は61.3%と半数以上の結果に。逆に行わなかった例では、5年生存率が16.5%となったのです。
肝臓切除という同じ方法をとったにも関わらず、ここまで差が出たということからも、ダウンステージング治療が生存期間を延ばす効果があるといえるでしょう。
記事の総評
がんが進行した状態で発見されることの多い肝臓がんに対して、レベルを下げる方法があるとは驚きの事実。 肝臓がんは進行がんの中でもほかの臓器への転移がしやすいので、進行レベルを下げてがん細胞を切除することができるならば、生存率向上や根治まで可能性が見えてきます。 今回まとめた「ダウンステージング」という治療法が、多くの医師や患者に認知されるようになればと願っています。
記事を執筆・解説した先生
奥田康司先生(久留米大学肝胆膵部門 教授)
肝臓がんの治療実績は全国平均を大きく上回り、世界でもトップレベルと言われる肝臓がん治療の名医です。 25年以上進行性の肝臓がん治療を行っており、進行がんであってもあきらめずに治療をすることが大事という思いをお持ちです。
大腸がんが肝転移したときの生存率や自覚症状について
自覚症状が無く進行していく肝臓がん。そもそも肝臓がんには、「原発性がん」と「転移性がん」がありますが、「転移性がん」の多くが大腸がんからの転移となっています。そこで、大腸がんが肝移転した際の自覚症状や生存率に関する注目記事をまとめてみました。
記事の要約
- 小さな大腸がんでも肝転移の可能性がある
- 肝転移したときの5年後生存率は上昇傾向
- 肝移転しても自覚症状はほぼないので注意
記事のポイント
小さな大腸がんでも肝転移の可能性がある
大腸がんの肝転移は、転移性肝臓がんの中でも最も多い種類です。もともと大腸がんは肺や脳などの重要な臓器に転移してしまう可能性が高く、その中でも最も転移しやすいのが肝臓なのです。これは肝臓が大腸から吸収された栄養分と一緒に、血液に含まれるがん細胞を受け止めてしまうからです。
大腸がんの肝転移では、患者本人の免疫力が強ければ、肝臓に入ったがん細胞を免疫細胞が壊し、転移を食い止めることがあります。しかし、小さな大腸がんでも肝転移の可能性がゼロではないと覚えておくほうがよいでしょう。
肝転移したときの5年後生存率は上昇傾向
がん治療では、5年後生存率が治療結果のひとつの目安となります。肝臓がんの5年後生存率は、肝切除の場合2017年で40~50%程度です。1980年代には30%以下であったことを考えると、医療が進歩したことがわかります。
2006年に行なわれた調査では大腸がんの肝転移に関するグレードを分け、各グレードによる5年後生存率を示しました。転移が少ない腫瘍が小さなものからA・B・Cとグレードを分け、それぞれの5年後生存率を調査。Aグループの生存率が約53%、Bグループは約30%、Cグループは約10%という数値が出ました。調査を行った当時は手術が多かったので、手術と並行して抗がん剤治療を行う現在は生存率やがん根治の可能性も上がっているでしょう。
肝移転しても自覚症状はほぼないので注意
肝臓がんは自覚症状がほとんどないのが実情で、これはほかのがんから転移した時も同じです。自覚症状のないうちに見つけることがベストですが、それは難しいでしょう。 自覚症状は、食欲不振や貧血のように判断しづらいものから、意識障害や吐血、腹部のしこりなどのように気づきやすいものまで、さまざまな症状があります。症状の中でも黄疸が出た場合は、肝臓の状態がかなり悪い状態であると考えられるので、注意が必要です。
記事の総評
肝転移が見つかれば、5年後生存率は約半数という結果があります。肝臓がんを早期発見するためにも、定期的な精密検査が必要と言えるでしょう。会社の人間ドックなどでは、血液検査や大腸内視鏡検査を取り入れるのも良い方法です。
記事を執筆・解説した先生
枝元良広先生(国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 肝胆膵外科医長)
年間手術数1,000件を超える名医として、高度な医療が必要な患者に対して実績があります。特に、専門である肝胆膵(かんたんすい)外科疾患や腹壁疾患においては、いかなる時でも患者の今後を考えた上での治療を実施することを念頭においているそうです。
転移性肝がん(肝転移)とは
普通の肝臓がんと、転移性の肝臓がんの違いとはどこ?また、肝臓に転移が多い理由や、再発での発見率が高いというのはなぜなのか?こういった疑問を解決するために、医師が答えたインタビュー記事を見つけたので紹介します。
解説している先生は、ステージが進んだ肝臓がんを切除することができる肝臓がん治療のエキスパートです。先生の経験や知識をもとに話が進むので、一見の価値ありです。
(解説:山本雄造先生/出典:Medical Note:https://medicalnote.jp/contents/180125-003-QZ)
記事の要約
- 乳がんや子宮がんから肝転移したケースもある
- 血液にのって肝臓に流れたがん細胞が増殖
- 肝転移したがん細胞が小さいと見つからないことも
記事のポイント
乳がんや子宮がんから肝転移したケースもある
転移性肝がんとは、肝臓以外で発生したがんが肝臓に転移したものです。転移は血管からが最も多くなっています。肝転移の原因となるがんの多くが、大腸や胃などの腹部消化器にできるがん。その中でも転移しやすいがんと、しにくいがんがあります。また女性では消化器系のがん以外にも、乳がんや子宮がんから肝転移したケースが報告されているようです。ただし、実際にはほとんどのがんが肝転移の可能性があるので、注意が必要です。
血液にのって肝臓に流れたがん細胞が増殖
がんが肝臓に転移しやすい原因は、大きく2つあります。 1つ目は、血液に乗ってがん細胞が流れてくるパターンです。肝臓以外で発生したがん細胞が血液を通して肝臓にたどり着き、そのまま腫瘍を形成します。2つ目が肝臓ががんになじみやすい臓器であるということです。肝臓に流れ着いたがん細胞が肝臓で増殖しなければ、肝臓がんとはなりません。転移元のがん細胞が肝臓との相性が良くなければ、定着しづらいと言うことです。同じ消化器系のがんでも大腸がんのほうが胃がんに比べて肝転移の確立が高いのは、大腸がんと肝臓の細胞の相性が良いからと考えられています。
肝転移したがん細胞が小さいと見つからないことも
肝転移は再発したときに見つかることがありますが、ほかのがんが治療後に転移したとは一概には言えません。大腸がんが発見されると、がんの詳しい部位や範囲を調べるためにCT検査を行ないます。その際に、肝転移が見つかることもありますが、肝臓のがん細胞がCTに映らないほど小さく、見逃されることも。その結果、大腸がんのみ治療が行なわれ、小さかった肝臓のがん細胞が大きくなって初めて発見されるのです。 これは現代医療の限界で、避けられない問題となっています。
記事の総評
転移性肝臓がんの怖さは、進行した状態で見つかるという点。 今回の先生の話であったように、小さながん細胞は見つけるのが難しいのが現状のようです。ただし、治療後の検査で見つかるからこそ進行した状態で見つかるのであって、こまめに検査を行なうことで進行レベルが低い状態で見つけることが可能です。 そのためには、がんの治療経過や再発確認のときにCTが無い場合は必ず入れるようにしましょう。そうすれば、万が一肝臓にがんが転移しても根治が可能です。自分の未来のために、適切な治療や検査を心がけましょう。
記事を執筆・解説した先生
山本雄造先生(秋田大学消化器外科学分野 教授)
肝臓や胆道、膵臓の疾患を専門とし、肝切除の経験が豊富なのはもちろんのこと、胆道・膵臓の治療経験も豊かです。肝静脈の根部に腫瘍が存在しているケースは通常切除不可能ですが、生体肝移植の技術を応用し、体内冷却肝灌流法を用いた「Ante-situm法」という方法で、肝切除を行なっています。ほかの医師では治療ができないような患者さんに対して、高難度手術を提供。患者さんにとってより良い治療を常に模索し、「簡単にはあきらめない」を信条として診療にあたっているそうです。
肝臓がんの標準治療と補完代替医療について
肝臓がんのステージ3になると、合併症により切除手術できないケースも少なくありません。しかし、標準治療をはじめ、それを補完する代替療法の研究も進んでおり、治療の望みは以前より大きいと言えます。このサイトでは、肝臓がんに対する各種標準治療のほか、標準治療を補完し、治療中や予後における生活の質(QOL)を高める効果が期待される代替医療について、詳しく解説しています。
代表的な補完代替医療
本サイトで紹介している主な代替医療は、以下の通りです。
代替医療について、効果や口コミ・評価を知りたい人は、以下を確認してください。
健康食品成分・サプリメントの注意点
「がんの医療現場における補完代替医療の利用実態調査」(2005年発表)によると、がん患者が利用している補完代替医療の中でも、圧倒的に多いのが「健康食品」の使用であり、実に96%以上を占めています。
しかし、数ある健康食品・サプリメントの中には、信頼できる裏付け(エビデンス・データや、臨床報告など)に乏しいものもあるのが現状。患者としては、できれば医師と相談のうえで、科学的根拠に基づいた選択に留意する必要があります。
このサイトでは、肝臓がん対策によく用いられる健康食品成分のエビデンスを調査してまとめていますので、参考にしてください。
肝臓がん対策に用いられる主な健康食品成分のエビデンスまとめを見る
肝臓がんステージ3に関する体験談
今のところの手立ては抗癌剤しかない
末期肝細胞癌と闘う53歳さん(男性)
K先生曰く「肝細胞癌。
つまり肝臓癌ですが、血管まで癌化しているので手術は無理です。
ほかの手段も今のところ無い(素人の私が画像を見ても肝臓は黒くしか写っておらず、生きていそうなところはせいぜい二割程度でした)今のところの手立ては抗癌剤しかないです」
私は「なぜ」と沈黙してしまいました。
また私はここでも余命を聞きました。
K先生は「6か月は多分難しい。
見立てでは遅くて3か月。
普通ならひと月。
突然明日来てもおかしくないです」と言われました。
E病院で聞いていたよりも診断された余命は短くなりました。
つまり、知らない間に私はもう余命終焉の時期の中に居たことになります。
この時もやはり「先生の誤診ではないのか。
お若いから経験が無いのではないのか。
切除しようとすれば出来るのではないのか」と思い現実逃避。
妻から見ても「怒り狂っていた」と後になって教えてもらいました。
「このような告知には、誰しも、否認、怒り、取引、うつ、受容という経緯を経る」と、ずっと後になって妻が教えてくれました。
彼女は元ナースです。
この初回の入院中に私はこのサイクルを全部通り、だんだん達観し出したようです。
しかし当時はまだ「全く余命を知らないまま突然死ぬよりも良かったじゃないか」そう無理にでも、無理にでも、自分に言い聞かすようにしました。
動けばくたびれるし
doramusumeさん(女性)
ハッキリ言って。
週末。
暇。
です。
入力のお仕事は来週から。
彼も暇そう。
だからと言って。
動けばくたびれるし。
何しろ、肝硬変に肝臓がん。
ステージ。
どうもサンらしい。
ε- (´ー`*)フッ・・3.。
って。
兼ね合いが。
ムツカシイ。
引用元:五月晴れの朝です(^▽^)/。 | 還暦を過ぎたdoramusumeが願う事~少しでも長く続けたいなっ^^;夫との穏やかな日々。。
手術 出来るか微妙・・・
りんごさん(女性)
夫は やはり肝臓がん でした
腫瘍は2個 ステージ3
検査は 内科でしてくれましたが
内科の先生のお勧めの治療は手術 とのこと
経験が多い先生に手術してもらった方が良い事
元の肝臓の状態があまり良くないので
(アルコールによる肝硬変を発症している)
手術 出来るか微妙・・・
腫瘍の場所も 難しい位置にあるとのこと
先生の方からセカンドオピニオンを薦められ
肝臓手術のスペシャリストの先生を紹介していただき
そちらの外科の先生の意見を聞退院してきました