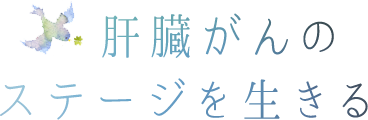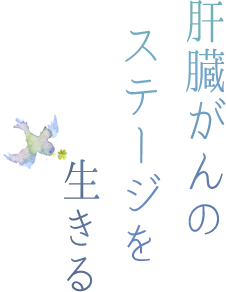肝臓がんのステージと肝障害度分類
このページでは、肝障害度分類について紹介しています。
肝障害度分類とは
肝臓がんの進行具合は医師により診断され、その状態によってステージ1~4までに分類されます。
ステージが進むほど病状が進行し、根治は困難に。生存率も低下していきますので、早期発見が要となります。
また肝臓がんの診療の際は、ステージ分けのほかに「肝機能がどのくらい保たれているか」もチェックされます。
それが「肝障害度分類」です。分類法には、以下の2つがあります。
■肝障害度分類…
腹水の有無、血清ビリルビン値、血清アルブミン値、ICG負荷試験値、
プロトロンビン活性値の4つの基準から肝障害度を調べ、状態をA~Cに分類する方法。
■Child-Pugh分類…
欧米でも採用される、世界基準の分類法。
肝性脳症の有無、腹水の有無、血清アルブミン値、血清総ビリルビン値、プロトロンビン活性値の5つの基準から調べ、
合計点で肝臓の障害度を評価する。結果はA~Cに分類される。
その治療法
肝障害度分類には上記2種類がありますが、いずれの方法でも結果はA~Cに分類されます。
肝機能の状態が最も良いのはAで、最も悪いのはC。Bはその中間ということになります。
 肝臓がんの治療法で最も効果的とされるのは「摘出手術」ですが、肝障害度分類がBまで進行してしまうと、
肝臓がんの治療法で最も効果的とされるのは「摘出手術」ですが、肝障害度分類がBまで進行してしまうと、
適用されるケースは全体の2割程度にまで低下してしまいます(Aの場合は7~8割)。
Cまで進行してしまうと、手術は困難となります。
また「マイクロ波凝固壊死療法」などの局所療法も、適用されるのはA~Bまで。
転移の見られるCでは、抗がん剤や放射線治療などがメインとなっていきます。
以上が肝障害度分類による治療法の概要です。しかし先述の通り、肝臓がん治療の現場では、
がん進行度のステージ分けも行われています。
治療法は双方の結果を見て、調整されていくことになるでしょう。
肝臓がんの標準治療と補完代替医療について
初期のステージでも、肝障害度分類により、肝臓の状態が手術に適していないと評価されれば、切除できない場合があります。しかし、標準治療をはじめ、それを補完する代替療法の研究も進んでおり、治療の望みは以前より大きいと言えます。このサイトでは、肝臓がんに対するさまざまな各種標準治療のほか、標準治療を補完し、治療中や予後における生活の質(QOL)を高める効果が期待される代替医療について、詳しく解説しています。
代表的な標準治療
本サイトで紹介している主な標準治療は、以下の通りです。
- 切除手術
- 肝臓移植
- 経皮的エタノール注入療法
- 肝動脈塞栓療法 など
標準治療について、詳しい内容を知りたい方は以下を確認してください。
代表的な補完代替医療
本サイトで紹介している主な代替医療は、以下の通りです。
- 健康食品・サプリメント
- 食事療法
- 漢方
- 免疫治療 など
代替医療について、効果や口コミ・評価を知りたい人は、以下を確認してください。