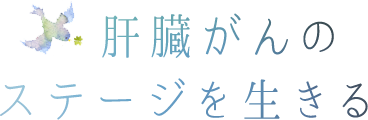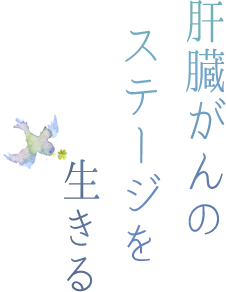検査方法は?
肝臓がんの検査方法について解説しています。最近注目を浴びている、尿検査によるがん検査もご紹介します。
肝臓がんは自覚症状がなく、おかしいな、と思った時には既にステージIV…ということが珍しくありません。そうなる前に早期発見をするためには、肝臓がんの検査をしっかりと受けておくことが大切です。
では、肝臓がんの検査はどのようにして行われるのでしょうか。肝臓がんの検査方法についてリサーチしてみました。
血液検査
がんに限らず、肝臓の機能は血液検査で知ることができます。血液検査で計る数値には、以下のようなものがあります。
ALT・AST
ALTとASTは、ともにアミノ酸をつくりだす酵素のこと。肝臓に存在する酵素です。
肝臓が障害を受けると血液中に流れ出るので、ALTとASTの値が高くなれば、肝臓に何らかの異常があったことを示します。ALTがASTを上回れば脂肪肝や慢性肝炎、ASTがALTを上回れば肝硬変や肝臓がん、アルコール性肝炎などが疑われます。
通常は両方の値が上がりますが、ALTの値だけが高ければ肝臓の病気、ASTだけが高ければ心筋梗塞や筋肉組織の異常と診断されます。
γ-GTP
肝臓や腎臓、すい臓、脾臓、小腸に存在する酵素で、肝臓や胆管の細胞が死ぬ時に血液中に流れ出します。
γ-GTPが高い場合も、やはり肝臓の異常が疑われます。
腫瘍マーカー
がん細胞が増殖した時につくられる、AFPやPIVKA-2などの特異物質による診断が腫瘍マーカーです。
腫瘍の有無の診断基準にはなりますが、小さいがんの時は腫瘍マーカーが基準値に満たないこともあるので、画像診断や肝生検が必要になります。
画像診断
CTやMRI、超音波などを使って肝臓の撮影をします。ここで肝臓がんと診断された場合は、太ももの付け根から肝動脈までカテーテルを通し、造影剤を挿入して動脈の状態を見る、腹部血管造影検査も行われます。
肝生検
肝臓に針を刺したり、腹部の外科手術で肝臓の病巣の一部を取り出すことで、がん細胞かどうかを診断する方法です。ほぼ確実に、がんかどうかを診断することができます。
線虫を使った尿検査に期待!
いま注目を浴びているのが、線虫を使った尿検査によるがん検査です。
C.elegansと呼ばれる線虫は、尿に含まれるがん患者特有の匂いに寄っていく習性があります。そのため、検査のための尿を一滴たらすだけで、その人ががんを患っているかどうかがわかるのです。
しかも早期がんでも発見でき、95.8%という高い精度でがんを発見しています。これが一回100~数百円というコストで可能なため、がん検査の飛躍的な向上に大きな期待が寄せられています。