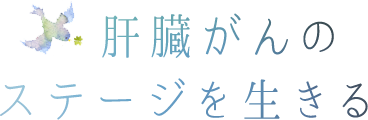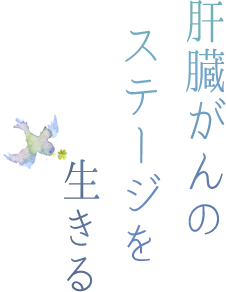肝臓がん関連ニュース
肝臓がんに関する注目のニュース記事をピックアップ。「10年生存率」・「新治療法」・「ビタミンDとがんリスクの関係」といったニュースを取り上げているので、ぜひご覧ください。
がん10年生存率は昨年調査よりやや上昇
(出典:サイエンスポータル)
国立がん研究センターによると、2001年から2004年の間にがんと診断された人の10年生存率は55.5%だったと発表されました。10年生存率の調査は今回で3回目の実施になります。昨年の調査に比べてがん10生存率はやや上昇という結果に。約5万7千人のデータを分析・集計し、部位別による生存率も発表しています。
難治がんの生存率は依然として低い水準
がん10年生存率は、がんと診断されてから一定期間経過したあとに生存している確率のことです。今回発表されたがん10年生存率は昨年と比べてやや上昇という結果でしたが、部位によっては生存率にかなりの差があるのが現状です。難治がんと呼ばれる肝臓がんやすい臓がんなどは、圧倒的に生存率は低いまま。難治がんの完治に向けての新たな治療法の開発が課題といえます。
がんになるリスクが低下?ビタミンD濃度との関係
(出典:マイナビニュース)
「血中のビタミンD濃度が高いとがんになるリスクが低くなる」といった研究結果を、国立がん研究センターが発表しました。対象は約34,000人で、長期間追跡した大規模な調査による結果だそうです。
血中のビタミンD濃度の高さで4つのグループに分けて、がん発症との関係を詳しく調べた結果がニュースとして取り上げられています。
8県に住む40~69歳の男女約3,4000人が対象
国立がん研究センターの研究結果から、血中のビタミンD濃度の高さによってがんを発症するリスクが低くなる傾向にあることがわかりました。調査対象は約34,000人とかなり多く、長期間にわたって追跡した結果ということもあり信頼性も高いです。この研究結果により、肝臓がんの完治に向けた新治療の開発につながる可能性があります。
肝臓の細胞の「若返り」に成功
(出典:財経新聞)
国立がん研究センターのグループが、肝臓の細胞の元となる「肝前駆細胞」に変化させることに成功したと発表。将来的に、重い肝臓病の新しい治療法の開発につながる成果として注目を浴びています。ヒトの肝臓の細胞を肝前駆細胞に変化させたのは世界で初とのことで、日本再生医療学会でも発表される予定です。
新治療法の開発につながる可能性がある
2種類の特殊な化合物を加えることで、肝臓の細胞の若返りに成功したと発表されています。若返りとは、肝臓の細胞の元となる「肝前駆細胞」へ変化させることに成功したということです。ヒトの肝臓の細胞を若返らせる手法は世界で初めてのことであり、新たな治療法の開発につながる可能性が高いと言えます。
近代グループが新治療法について発表
(出典:産経WEST)
近畿大医学部の工藤正俊教授らの研究グループが、切除不能となった肝臓がん患者を対象に臨床試験を実施。2つの治療法を併用することで、がんの進行を遅らせるといった研究結果を発表しました。有効性と安全性を世界で初めて実証した研究結果となります。
組み合わせた治療法は、「肝動脈化学塞栓療法(TACE)」と抗がん剤の「ソラフェニブ」の投与です。
新治療法の実証は肝臓がん患者の希望に
がんの進行を遅らせる研究結果が発表されたというニュースは、肝臓がん患者にとって希望となるでしょう。この研究結果は国内の33施設を対象に、平成22~29年と長い期間によって実証されたそうで、信頼性も高いと言えます。この手法が標準治療となり、今後は完治に向けての治療法の開発が課題となっていきます。